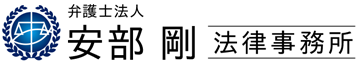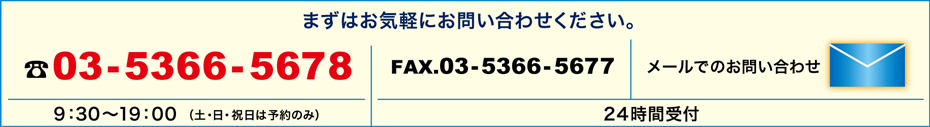と言われる弁護士でありたい。
円滑な相続のために。
| 自分が亡くなった後は子供達に仲良く暮らしてほしいというのが親の願いですが、相続争いが発生する大きな原因のひとつは、遺言書が作成されていない事にあります。 遺言書が作成されていれば被相続人の意向が明確ですので相続人間の協議も円滑に進めることができますし、 公正証書遺言があれば不動産の登記手続などの遺産分割をスムーズに行うことができます。 もっとも、遺言書を作成する際には法律で決められた条件をクリアする必要があり、必要な条件を満たしていないと遺言書自体が無効になってしまいますので、作成される場合には必ず専門家である弁護士にご相談ください。 | |
| 遺言状の種類 | 自筆証書遺言 |
自筆証書遺言とは、遺言書の全文を自分で記載し、日付及び氏名も自署した上で、押印がされた遺言書のことをいいます(民法第968 条)。 簡単に作成できるので自筆証書遺言も少なくありませんが、遺言書自体の有効性が問題となるケースもありますので注意が必要です。 | |
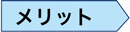 | 被相続人が好きな時に作成することができ、内容を変更することも容易に可能である。 |
 | 遺言書を発見した人によって遺言書が破棄されてしまうなどの危険性がある。 |
公正証書遺言 全国各地にある公証役場において、公証人のよって作成される遺言書のことをいいます(民法第969 条)。 公証人という公的な立場にある人が作成し、原本が公証役場で保管されますので安心です。 | |
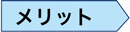 | 公証人という公的な立場の人間が被相続人の意思能力を確認した上で作成するため、遺言状の効力について争われる心配がない。 |
 | 作成費用がかかる。 |
| 相続人の順位と 法定相続分 | 配偶者(妻や夫)と子供がいるケース |
配偶者と子が相続人となり、法定相続分は妻が2分の1、子が2分の1となります。子供が複数いる場合には2分の1の割合を子供の人数で案分することになりますので、子供が2人いる場合の法定相続分は子供1人当たり4分の1となります。 配偶者しかいないケース 配偶者と直系尊属(被相続人の両親又は祖父母)が相続人となり、法定相続分は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1になります。 被相続人の直系尊属が亡くなっていた場合には、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となり、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。 配偶者も子供もいないケース 配偶者も子供もいない場合には、まずは被相続人の直系尊属(両親又は祖父母)が相続人となり、直系尊属が全員亡くなっている場合には、兄弟姉妹が相続人となります。 | |
| 遺留分減殺請求 | 遺留分とは、遺言によっても侵害することのできない、法定相続人保護の見地から認められている最低限の相続財産の割合です(民法第1028 条)。 |
例:相続人は妻と子供1人。 子供には遺留分が認められているため、法定相続分の50%である4分の1は自分の相続分であることを主張することができます。 遺留分は被相続人が亡くなってから(又は亡くなったことを知ってから)一定の期間内に権利行使をしなければ権利行使ができなくなってしまいますので、相続発生の事実を認識されたらすぐにご相談ください。 | |
| 相続放棄 | 被相続人に借金などの消極的財産(マイナスの財産)がある場合には、相続人が債務を承継することになりますので、相続放棄を検討する必要があります。 |
例えば、預金や不動産が1000万円あったとしても、借金が2000万円あれば、結局相続人は1000万円の借金を負うことになってしまいます。 このような不都合を回避するために、民法では相続人たる地位を放棄することが認められており、これを相続放棄といいます。 上記の例のようにプラスの財産よりマイナスの財産が多い場合だけでなく、マイナスの財産しかない場合にも相続放棄をする必要があります。 但し、相続放棄が出来る期間は原則として被相続人が亡くなってから3カ月以内と定められていますので、相続放棄が必要なケースでは早急に弁護士にご相談ください。 |